オリジナル創作ブログです。ジャンルは異世界ファンタジー中心。
放置中で済みません。HNを筧ゆのからAlikaへと変更しました。
2026.01.21
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2009.07.27
「明日、花が咲くように」 十二章 3
先日、高熱で寝込んでいる間、ずっと昔の夢を見ていた。
熱で気が弱くなったのか、ひどく感傷的な夢だった。
あるいはそれは、あの実験で、身近な人々の心の一部を「声」として聞いてしまったのも、理由の一つかもしれない。
物心つく前、僕には世話をしてくれる一人の女性がいた。
僕はその人を「母」という存在なのかと、朧気に思っていた。
まだ、王子宮に移される前……、後宮で、本来なら母親の元で育つはずの頃の話だ。
周りの皆が僕を怖れ近寄ってこないのは、その頃の僕にとって至極当たり前の風景であり、何ら不思議に思う事もなく。差し伸べられるたった一つの手だけが、僕の世界のすべてだった。
その人が亡くなって、僕は喪失感というものを知る。
そして、自分がこれからどうやって立っていけばいいか、誰も示してくれないのに大きな不安を覚えた。
独りきり。それを寂しいと思っても、誰かに手を伸ばしても届かない。そんな日々が続いた。
何も知らずとも、自分が悪いものであるのだと、漠然と悟らざるをえなかった。
五歳になって王子宮に移ると、ジークフリード殿下が僕の眼を見て、「不吉な子供だ!」と暴力を振るおうとし、セレナ殿下には「そなたが母上を殺したのだ!」と、きつく罵られた。
自分が嫌われる原因が色違いの瞳にあるのだと、ジークフリード殿下の言葉で初めて知った。
後宮にいた頃、一人だけ手を差し伸べてくれていた人が実母ではなく、セレナ殿下の母上であったのだとも、その頃になってようやく知った。
王の妾妃であったアリア殿は、後宮において唯一、色違いの瞳を持つ僕の世話を買って出てくれたらしい。そして、僕が三歳の頃に病で亡くなったのだ。
彼女が亡くなったのは忌み子の世話をしたせいだと囁かれ、セレナ殿下はその噂を信じ、僕が母上を殺したのだと責め立てたのだ。
王宮で孤立する僕を庇ってくれたのは、長女のグレイシア殿下だった。
弟妹が度を過ぎる言動をする度に、「不確かな噂に翻弄されて、血の繋がった弟を虐げるような真似はおやめなさい」と、彼らを静かに諭してくれた。
ただあの方は、硬質で近づき難い雰囲気があり、思い返してみると距離があったようにも思う。
(そういえばあの頃は、アルフォンソ殿下とは顔を合わさなかったな)
同い年の兄弟。聡明と噂に高い彼の顔を、その頃僕に知らずにいた。
同じ時期に後宮から王子宮に移ってきたはずなのに、後宮にいた頃も、王子宮に移った後も、彼を見掛けた覚えは一度もなかった。
(だからかな。僕にとって近しい人といえば、ヒースとギーレンだけだった)
宮廷魔術師長のギーレンが僕の状況を憂いて、穏やかに労わってくれた。
そして彼の弟子となったヒースが、親しい友人として接してくれた。
ヒースととともに学んだあの頃が、幼い頃の記憶の中で一番楽しい思い出だ。
彼らと出会わなければ、僕は自分の置かれている状況を客観的に判断する術もなく、ただ暴力に怯え、孤独を孤独とも思わず、たった一人で途方に暮れて過ごしたに違いない。
←back 「明日、花が咲くように」 目次へ next→
ネット小説ランキング>【異世界FTシリアス/異世界恋愛シリアス】部門>明日、花が咲くようにに投票
ネット小説の人気投票です。投票していただけると励みになります。(週1回)
「NEWVEL」小説投票ランキング
「Wandering Network」アクセスランキング
「HONなび」投票ランキング
熱で気が弱くなったのか、ひどく感傷的な夢だった。
あるいはそれは、あの実験で、身近な人々の心の一部を「声」として聞いてしまったのも、理由の一つかもしれない。
物心つく前、僕には世話をしてくれる一人の女性がいた。
僕はその人を「母」という存在なのかと、朧気に思っていた。
まだ、王子宮に移される前……、後宮で、本来なら母親の元で育つはずの頃の話だ。
周りの皆が僕を怖れ近寄ってこないのは、その頃の僕にとって至極当たり前の風景であり、何ら不思議に思う事もなく。差し伸べられるたった一つの手だけが、僕の世界のすべてだった。
その人が亡くなって、僕は喪失感というものを知る。
そして、自分がこれからどうやって立っていけばいいか、誰も示してくれないのに大きな不安を覚えた。
独りきり。それを寂しいと思っても、誰かに手を伸ばしても届かない。そんな日々が続いた。
何も知らずとも、自分が悪いものであるのだと、漠然と悟らざるをえなかった。
五歳になって王子宮に移ると、ジークフリード殿下が僕の眼を見て、「不吉な子供だ!」と暴力を振るおうとし、セレナ殿下には「そなたが母上を殺したのだ!」と、きつく罵られた。
自分が嫌われる原因が色違いの瞳にあるのだと、ジークフリード殿下の言葉で初めて知った。
後宮にいた頃、一人だけ手を差し伸べてくれていた人が実母ではなく、セレナ殿下の母上であったのだとも、その頃になってようやく知った。
王の妾妃であったアリア殿は、後宮において唯一、色違いの瞳を持つ僕の世話を買って出てくれたらしい。そして、僕が三歳の頃に病で亡くなったのだ。
彼女が亡くなったのは忌み子の世話をしたせいだと囁かれ、セレナ殿下はその噂を信じ、僕が母上を殺したのだと責め立てたのだ。
王宮で孤立する僕を庇ってくれたのは、長女のグレイシア殿下だった。
弟妹が度を過ぎる言動をする度に、「不確かな噂に翻弄されて、血の繋がった弟を虐げるような真似はおやめなさい」と、彼らを静かに諭してくれた。
ただあの方は、硬質で近づき難い雰囲気があり、思い返してみると距離があったようにも思う。
(そういえばあの頃は、アルフォンソ殿下とは顔を合わさなかったな)
同い年の兄弟。聡明と噂に高い彼の顔を、その頃僕に知らずにいた。
同じ時期に後宮から王子宮に移ってきたはずなのに、後宮にいた頃も、王子宮に移った後も、彼を見掛けた覚えは一度もなかった。
(だからかな。僕にとって近しい人といえば、ヒースとギーレンだけだった)
宮廷魔術師長のギーレンが僕の状況を憂いて、穏やかに労わってくれた。
そして彼の弟子となったヒースが、親しい友人として接してくれた。
ヒースととともに学んだあの頃が、幼い頃の記憶の中で一番楽しい思い出だ。
彼らと出会わなければ、僕は自分の置かれている状況を客観的に判断する術もなく、ただ暴力に怯え、孤独を孤独とも思わず、たった一人で途方に暮れて過ごしたに違いない。
←back 「明日、花が咲くように」 目次へ next→
ネット小説ランキング>【異世界FTシリアス/異世界恋愛シリアス】部門>明日、花が咲くようにに投票
ネット小説の人気投票です。投票していただけると励みになります。(週1回)
「NEWVEL」小説投票ランキング
「Wandering Network」アクセスランキング
「HONなび」投票ランキング
PR
最新記事
目次
アーカイブ
カテゴリー





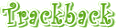
 管理画面
管理画面
