オリジナル創作ブログです。ジャンルは異世界ファンタジー中心。
放置中で済みません。HNを筧ゆのからAlikaへと変更しました。
2026.01.21
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2009.06.16
「明日、花が咲くように」 七章 8
「ギーレン様といえば、宮廷魔術師長の?」
スノウ嬢が嬉しそうな声を上げる。
魔術師を目指す者にとって、宮廷魔術師長という立場に何十年も立ち続ける彼は、憧れの存在なのだろう。
「うん。彼はヒースの魔術の師匠だった人でね。彼に師事する為にヒースが宮廷にいた時期があって、その頃僕もギーレンから様々な知識を学ばせてもらっていたから、ヒースとは幼馴染みみたいなものなんだ」
説明しながら、そういえば、僕とヒースの関係をスノウ嬢にきちんと話すのはこれが初めてだっけ、と気づく。
最初に会った時から妙に息が合って、ヒースをからかいつつ楽しく話をしてばかりだったものだから、意外と基本的な情報の交換をしてなかった。
「師匠のお師匠さまは、あの高名なギーレン様だったのですか。それに、師匠が宮廷で過ごした時期もあったなんて知りませんでした。道理でお二人は仲が良い訳ですね」
「ちょっと待てっ。どこをどう見たらそう見える!?」
「ふふ、照れなくてもいいじゃない。実際仲良しなんだから」
「どこがだ!」
ヒースがものすごく嫌そうに反発する。でも実際、気心が知れている相手じゃなければ、こんなふうに軽口なんて叩けない。そういうのを素直に認めないところが、ヒースの面白いところでもあるんだけど。
「ヒースは数年でギーレンを超えて、国一番の魔術師と言われるようになった。そしてその後、個人で研究がしたいからと、宮仕えの誘いを断って宮廷から出ていったんだ」
宮廷魔術師長であり彼の師匠であるギーレンが、ヒースの実力を自分より上だと公に認めた時点で、ヒースは自動的に「国で一番の魔術師である」と認定された。
それも当然だ。それまでずっと何十年も、ギーレンこそが国一番の実力者であると言われ続けてきたのだから。
宮仕えを拒んだ件に関しては、当時かなりの反発を呼んだ。だけどそれも結局は、ヒースの飛びぬけた実力を前に沈黙した。彼を粗雑に扱って他国に行かれてしまうよりは、できうる限り優遇して、この国にい続けてもらった方が賢いと中枢に思わせるだけの実力と頭脳を、ヒースが備えていたからだ。
「宮廷魔術師となるのは大変名誉な事ですが、国務で忙しく、研究だけに時間を割けないという面もありますからね。研究第一の師匠にはあまり向いていなかったのでしょう」
「そうだね。それにヒースってこういう性格だから、他人に仕えるとかそういうのが、そもそも向いてないしねえ」
スノウ嬢と二人で苦笑を交し合って、肩を竦めて、呆れた顔をしてみせる。
それに文句を言いたげなヒースに、僕が「ごめん、本題がずれたね」と微笑むと、何を言っていいのか迷う表情で黙り込んだ。
スノウ嬢も、話がずれたのを承知で、あえて僕の話に付き合ってくれていたのだろう。
彼らは表向きは平静に振舞っていても、内心では僕の心情を、とても気遣ってくれている。
王と正妃の「声」を意図的に話題から外しているのも、それに触れたら余計に僕を傷つけてしまうだけだとわかっているからだ。
(知りたくもなかったあの人たちの心情は、多分、こうして改めて「声」として聞かなくても、僕に対するその態度で、気づいてた。わかってた)
だから今更傷ついたりはしない。
僕はそう、自分に強く言い聞かせる。
「グレイシア殿下もそうだけど、他にも、僕の剣の師の声もなかったと思う」
逸れた本筋に話を戻す。
「剣の師匠ですか?」
「そう、僕の頼みに応えて、剣術を教えてくれた人。そして、そのせいで王の近衛から外された騎士」
まだ知り合って日が浅いから、スノウ嬢が僕の事情を詳しく知らないのは当たり前だ。だから僕はわかりやすく説明する。
「サリア・ロッドベルトか」
ヒースは心当たりがあるから、「確かに、あの男の声が聞こえないのはおかしいな」と静かに同意した。
「うん。「近しい人」の条件に当て嵌めるなら、彼の声が聞こえなかったのはおかしいと思う」
恨みつらみが思いとなって届くというなら、彼の声がないはずがない。恨まれていないなんて、自分に都合の良い考えはとても持てない。
「サリアは王の近衛隊の副隊長だったのに、僕に剣を教えたせいで、王の不興を買ってしまったんだ。そして近衛の任を解かれ、国で一番不安定な情勢の国境へ飛ばされた」
「……そんな」
スノウ嬢が口元に手を当てて、どうしようもなく悔しそうな顔をする。
そんな理不尽がまかり通る程に、色違いの瞳を持つ僕は、国にとって邪魔な存在だったのだ。
そんな僕に気をかけてくれたからこそ、サリアは理不尽な目にあった。
同じように僕を気にかけたギーレンには、魔術師長としての任を決して解けないだけの確固たる基盤があった。
サリアには、どうしても近衛の任を解かずにおけるだけの理由がなかった。
たったそれだけの違いで、彼の未来は潰された。
「ならば、第一王女と同じく、「声」が届く範囲外だったと考えるのが妥当だろう。今回の実験では、周りの精霊すべてを引き剥がしてはいないしな」
「声が届いたのは、王都近辺の範囲内だけだったという事ですか? ならばもし、精霊たちがすべてが離れたら、もっと遠くの相手の「声」まで聞こえるようになるのでしょうか?」
「あるいは、エディアローズにとって関わりの薄い相手の「声」までが、無差別に聞こえるようになるか」
「それ、想像しただけで寒気がするよ」
どちらだったとしても、僕の精神を蝕む猛毒になる。特にヒースの言った方だったら最悪だ。
国中から始終「声」が聞こえ続けたりすれば、正気でいられる自信などない。
「どちらにしても、同じ方法でこれ以上の実験はしない。また、別の方向からの手段を考える」
「そっか」
それで実験はお開きとなった。
僕はカリクからシュシュを返してもらって、ヒースの屋敷を後にする。
僕の肩に乗って頬に擦り寄ってくる小さな友人に、僕はしたり顔で説教する。
「君はもう、藁人形から貰った怪しすぎる餌なんて、食べちゃ駄目だからね」
「キュ?」
目を見開いて、不思議そうに首を傾げる仕草が可愛らしい。
言語の通じない相手にこんな事を言い聞かせても仕方ないのだけど、それでも言わずにいられなかった。
ただ、与えられた餌が毒じゃなかっただけマシだとも思う。
それでも帰ったら、シュシュをこっそり肥満にする嫌がらせを企んでいる次兄と、きっちり話をつけないと。
他の兄弟に関しては、まあ、……心の中の「負の感情」が、すでに通常の態度にそのまま出ているような人たちばかりなので、何を言っても無駄だろう。
言ってしまえば、あまり害のないものでしかないのだし。
(本当に、僕が懸念していたよりずっと害がなくて、拍子抜けかも)
本当の意味での「悪意」を持っていたのは、多分、両親だけだった。
近しい人や、血の繋がった相手すべてを否定する必要はなかった。その事に笑ってしまう。
それが救いになるのかどうか、僕にはまだ、わからなかったけれど。
←back 「明日、花が咲くように」 目次へ next→ 「八章」
ネット小説ランキング>【異世界FTコミカル/異世界FTシリアス】部門>明日、花が咲くようにに投票
ネット小説の人気投票です。投票していただけると励みになります。(週1回)
「NEWVEL」小説投票ランキング
「Wandering Network」アクセスランキング
「HONなび」投票ランキング
スノウ嬢が嬉しそうな声を上げる。
魔術師を目指す者にとって、宮廷魔術師長という立場に何十年も立ち続ける彼は、憧れの存在なのだろう。
「うん。彼はヒースの魔術の師匠だった人でね。彼に師事する為にヒースが宮廷にいた時期があって、その頃僕もギーレンから様々な知識を学ばせてもらっていたから、ヒースとは幼馴染みみたいなものなんだ」
説明しながら、そういえば、僕とヒースの関係をスノウ嬢にきちんと話すのはこれが初めてだっけ、と気づく。
最初に会った時から妙に息が合って、ヒースをからかいつつ楽しく話をしてばかりだったものだから、意外と基本的な情報の交換をしてなかった。
「師匠のお師匠さまは、あの高名なギーレン様だったのですか。それに、師匠が宮廷で過ごした時期もあったなんて知りませんでした。道理でお二人は仲が良い訳ですね」
「ちょっと待てっ。どこをどう見たらそう見える!?」
「ふふ、照れなくてもいいじゃない。実際仲良しなんだから」
「どこがだ!」
ヒースがものすごく嫌そうに反発する。でも実際、気心が知れている相手じゃなければ、こんなふうに軽口なんて叩けない。そういうのを素直に認めないところが、ヒースの面白いところでもあるんだけど。
「ヒースは数年でギーレンを超えて、国一番の魔術師と言われるようになった。そしてその後、個人で研究がしたいからと、宮仕えの誘いを断って宮廷から出ていったんだ」
宮廷魔術師長であり彼の師匠であるギーレンが、ヒースの実力を自分より上だと公に認めた時点で、ヒースは自動的に「国で一番の魔術師である」と認定された。
それも当然だ。それまでずっと何十年も、ギーレンこそが国一番の実力者であると言われ続けてきたのだから。
宮仕えを拒んだ件に関しては、当時かなりの反発を呼んだ。だけどそれも結局は、ヒースの飛びぬけた実力を前に沈黙した。彼を粗雑に扱って他国に行かれてしまうよりは、できうる限り優遇して、この国にい続けてもらった方が賢いと中枢に思わせるだけの実力と頭脳を、ヒースが備えていたからだ。
「宮廷魔術師となるのは大変名誉な事ですが、国務で忙しく、研究だけに時間を割けないという面もありますからね。研究第一の師匠にはあまり向いていなかったのでしょう」
「そうだね。それにヒースってこういう性格だから、他人に仕えるとかそういうのが、そもそも向いてないしねえ」
スノウ嬢と二人で苦笑を交し合って、肩を竦めて、呆れた顔をしてみせる。
それに文句を言いたげなヒースに、僕が「ごめん、本題がずれたね」と微笑むと、何を言っていいのか迷う表情で黙り込んだ。
スノウ嬢も、話がずれたのを承知で、あえて僕の話に付き合ってくれていたのだろう。
彼らは表向きは平静に振舞っていても、内心では僕の心情を、とても気遣ってくれている。
王と正妃の「声」を意図的に話題から外しているのも、それに触れたら余計に僕を傷つけてしまうだけだとわかっているからだ。
(知りたくもなかったあの人たちの心情は、多分、こうして改めて「声」として聞かなくても、僕に対するその態度で、気づいてた。わかってた)
だから今更傷ついたりはしない。
僕はそう、自分に強く言い聞かせる。
「グレイシア殿下もそうだけど、他にも、僕の剣の師の声もなかったと思う」
逸れた本筋に話を戻す。
「剣の師匠ですか?」
「そう、僕の頼みに応えて、剣術を教えてくれた人。そして、そのせいで王の近衛から外された騎士」
まだ知り合って日が浅いから、スノウ嬢が僕の事情を詳しく知らないのは当たり前だ。だから僕はわかりやすく説明する。
「サリア・ロッドベルトか」
ヒースは心当たりがあるから、「確かに、あの男の声が聞こえないのはおかしいな」と静かに同意した。
「うん。「近しい人」の条件に当て嵌めるなら、彼の声が聞こえなかったのはおかしいと思う」
恨みつらみが思いとなって届くというなら、彼の声がないはずがない。恨まれていないなんて、自分に都合の良い考えはとても持てない。
「サリアは王の近衛隊の副隊長だったのに、僕に剣を教えたせいで、王の不興を買ってしまったんだ。そして近衛の任を解かれ、国で一番不安定な情勢の国境へ飛ばされた」
「……そんな」
スノウ嬢が口元に手を当てて、どうしようもなく悔しそうな顔をする。
そんな理不尽がまかり通る程に、色違いの瞳を持つ僕は、国にとって邪魔な存在だったのだ。
そんな僕に気をかけてくれたからこそ、サリアは理不尽な目にあった。
同じように僕を気にかけたギーレンには、魔術師長としての任を決して解けないだけの確固たる基盤があった。
サリアには、どうしても近衛の任を解かずにおけるだけの理由がなかった。
たったそれだけの違いで、彼の未来は潰された。
「ならば、第一王女と同じく、「声」が届く範囲外だったと考えるのが妥当だろう。今回の実験では、周りの精霊すべてを引き剥がしてはいないしな」
「声が届いたのは、王都近辺の範囲内だけだったという事ですか? ならばもし、精霊たちがすべてが離れたら、もっと遠くの相手の「声」まで聞こえるようになるのでしょうか?」
「あるいは、エディアローズにとって関わりの薄い相手の「声」までが、無差別に聞こえるようになるか」
「それ、想像しただけで寒気がするよ」
どちらだったとしても、僕の精神を蝕む猛毒になる。特にヒースの言った方だったら最悪だ。
国中から始終「声」が聞こえ続けたりすれば、正気でいられる自信などない。
「どちらにしても、同じ方法でこれ以上の実験はしない。また、別の方向からの手段を考える」
「そっか」
それで実験はお開きとなった。
僕はカリクからシュシュを返してもらって、ヒースの屋敷を後にする。
僕の肩に乗って頬に擦り寄ってくる小さな友人に、僕はしたり顔で説教する。
「君はもう、藁人形から貰った怪しすぎる餌なんて、食べちゃ駄目だからね」
「キュ?」
目を見開いて、不思議そうに首を傾げる仕草が可愛らしい。
言語の通じない相手にこんな事を言い聞かせても仕方ないのだけど、それでも言わずにいられなかった。
ただ、与えられた餌が毒じゃなかっただけマシだとも思う。
それでも帰ったら、シュシュをこっそり肥満にする嫌がらせを企んでいる次兄と、きっちり話をつけないと。
他の兄弟に関しては、まあ、……心の中の「負の感情」が、すでに通常の態度にそのまま出ているような人たちばかりなので、何を言っても無駄だろう。
言ってしまえば、あまり害のないものでしかないのだし。
(本当に、僕が懸念していたよりずっと害がなくて、拍子抜けかも)
本当の意味での「悪意」を持っていたのは、多分、両親だけだった。
近しい人や、血の繋がった相手すべてを否定する必要はなかった。その事に笑ってしまう。
それが救いになるのかどうか、僕にはまだ、わからなかったけれど。
←back 「明日、花が咲くように」 目次へ next→ 「八章」
ネット小説ランキング>【異世界FTコミカル/異世界FTシリアス】部門>明日、花が咲くようにに投票
ネット小説の人気投票です。投票していただけると励みになります。(週1回)
「NEWVEL」小説投票ランキング
「Wandering Network」アクセスランキング
「HONなび」投票ランキング
PR
最新記事
目次
アーカイブ
カテゴリー





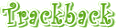
 管理画面
管理画面
