オリジナル創作ブログです。ジャンルは異世界ファンタジー中心。
放置中で済みません。HNを筧ゆのからAlikaへと変更しました。
2026.01.21
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2009.05.23
「明日、花が咲くように」 二章 3
もうしばらく、魔道具の掃除や手入れなどを徹底的にさせて根性を試そうかと思っていたが、現在どれだけの能力を持っていてどれくらい戦えるのか、どうにも気になってしまった。
魔術師としての腕がどうとかではなく、護身術がどの程度なのかを知っておかなければ、この女を馬で通わせるのに不安が残るからだ。
「腕を見てやる」と僕が言うと、驚いた顔で、「師匠って意外と面倒見が良いのですね」と感心された。……どこまでも失礼な女だ。
使役する精獣を召喚して戦わせても良かったが、変質の魔力がどう働いて、万一の事態が起きないとも限らない。
僕は変質の魔力性質について、国内ではもっとも研究を進めている第一人者であると自負しているが、それでも、こいつ程にまで傾いた能力の持ち主は、これまで見た事がなかった。
ある意味、貴重な研究素材とも言える。
僕は普段の黒いローブから、動きやすい服に着替えて裏庭に出る。
シズヴィッドもローブを脱いで、ズボンにシャツとベストだけの軽装になっていた。いつもは後ろで一つに括っている髪も、高い位置まで結い上げて三つ編みにしてまとめている。
その軽装から見ても、やはり変質と相性が良いとされる、格闘系の戦い方をするようだ。
そういえば、僕に紹介状を書いてよこしたこいつの前の師は、「疾風のペレ」と呼ばれる、接近戦を得意とする珍しいタイプの魔術師だ。
彼は魔術の研究分野においては特に功績を残していないので、魔術師としての地位は低いが、13年前、国境で紛争があった際、ナデュワードの砦という最前線となった戦場において、一人で何十人もの敵を相手にして勝利したという武勇伝がある。
かくいう僕自身、その紛争鎮圧に参加しており、その活躍をこの目で直に見た。戦い方が独特だった事もあり、わりと印象に残っている。
この国の魔術師は後方支援でしか役に立たない貧弱なタイプが多いのだが、あのペレの弟子だったというなら、シズヴィッドもまた、接近戦を得意としても不思議はない。
「素手ですか?」
「天才と名高い僕が、見習いのおまえに遅れを取るとでも?」
僕の本来の戦闘スタイルは杖を使っての魔術と杖術が主だが、たとえ武器を使わずとも、見習い程度に負ける気はない。接近戦でも戦えるだけの実力はある。
「それもそうですね、では、遠慮なく行かせていただきます」
(ナックル!?)
両手にはめた金属製のナックルの鈍い輝きに、一瞬気を取られた。いくら格闘系と予想していたとはいえ、女がその武器はないだろう、と。
僕が呆気に取られている隙に素早く走りこんで距離をつめたシズヴィッドが、走ってきた勢いに乗せて本当に何の遠慮もなく、鳩尾を狙って鋭い蹴りを放ってくる。
風切り音と、風圧が一気に押し寄せてくる。咄嗟に身を引いてその蹴りを躱すが、間近を通り過ぎていったブーツの重心と圧力の違和感に気づいて眉を顰める。
(こいつ、ブーツの踵とつま先にも、金属を仕込んでいるのか!?)
ナックルといい、仕込み靴といい、一朝一夕で使いこなせる武器ではない。ましてや女が使うには金属の重さがネックになって使い辛い武器の筈である。
それを扱い慣れている速さと動作でもって繰り出してくる相手に、僕は僕は油断ばかりはしていられないようだと、気を取り直して応戦した。
時間にして、十数分は経っただろうか。
脳内ではその何千倍もの思考速度だった気がするが。
「よし、もういいだろう」
「はい! ありがとうございました!」
ビシッと、軍隊顔負けのきっちりした敬礼をして、シズヴィッドが直後に、派手に地面へと倒れこむ。
僕は、乱れた息を整えながら頬を伝う汗を拭う。額に張り付く髪が鬱陶しい。
(か、勝ったか……)
師匠としての面目は、一応、守れたらしい。
しかし、ここまで梃子摺るハメになるとはまったく思っていなかった。
……想定外に、かなり、……いや、ものすごく強かった。
これだけの実力があれば、仮に暴漢に襲われたとしても返り討ちにできる。
それどころか、襲ってきた暴漢を警備兵に突き出して、褒賞金でも貰って、家計の足しにでもしていそうな気がしてきた。
きっとそうだ。そうに違いない。
(この女は、心配するだけ無駄だ)
ものすごい徒労感に襲われて、僕もまた、地面の上に座りこんだ。
←back 「明日、花が咲くように」 目次へ next→
「NEWVEL」小説投票ランキング(月1回)
「HONなび」投票ランキング(日1回)
魔術師としての腕がどうとかではなく、護身術がどの程度なのかを知っておかなければ、この女を馬で通わせるのに不安が残るからだ。
「腕を見てやる」と僕が言うと、驚いた顔で、「師匠って意外と面倒見が良いのですね」と感心された。……どこまでも失礼な女だ。
使役する精獣を召喚して戦わせても良かったが、変質の魔力がどう働いて、万一の事態が起きないとも限らない。
僕は変質の魔力性質について、国内ではもっとも研究を進めている第一人者であると自負しているが、それでも、こいつ程にまで傾いた能力の持ち主は、これまで見た事がなかった。
ある意味、貴重な研究素材とも言える。
僕は普段の黒いローブから、動きやすい服に着替えて裏庭に出る。
シズヴィッドもローブを脱いで、ズボンにシャツとベストだけの軽装になっていた。いつもは後ろで一つに括っている髪も、高い位置まで結い上げて三つ編みにしてまとめている。
その軽装から見ても、やはり変質と相性が良いとされる、格闘系の戦い方をするようだ。
そういえば、僕に紹介状を書いてよこしたこいつの前の師は、「疾風のペレ」と呼ばれる、接近戦を得意とする珍しいタイプの魔術師だ。
彼は魔術の研究分野においては特に功績を残していないので、魔術師としての地位は低いが、13年前、国境で紛争があった際、ナデュワードの砦という最前線となった戦場において、一人で何十人もの敵を相手にして勝利したという武勇伝がある。
かくいう僕自身、その紛争鎮圧に参加しており、その活躍をこの目で直に見た。戦い方が独特だった事もあり、わりと印象に残っている。
この国の魔術師は後方支援でしか役に立たない貧弱なタイプが多いのだが、あのペレの弟子だったというなら、シズヴィッドもまた、接近戦を得意としても不思議はない。
「素手ですか?」
「天才と名高い僕が、見習いのおまえに遅れを取るとでも?」
僕の本来の戦闘スタイルは杖を使っての魔術と杖術が主だが、たとえ武器を使わずとも、見習い程度に負ける気はない。接近戦でも戦えるだけの実力はある。
「それもそうですね、では、遠慮なく行かせていただきます」
(ナックル!?)
両手にはめた金属製のナックルの鈍い輝きに、一瞬気を取られた。いくら格闘系と予想していたとはいえ、女がその武器はないだろう、と。
僕が呆気に取られている隙に素早く走りこんで距離をつめたシズヴィッドが、走ってきた勢いに乗せて本当に何の遠慮もなく、鳩尾を狙って鋭い蹴りを放ってくる。
風切り音と、風圧が一気に押し寄せてくる。咄嗟に身を引いてその蹴りを躱すが、間近を通り過ぎていったブーツの重心と圧力の違和感に気づいて眉を顰める。
(こいつ、ブーツの踵とつま先にも、金属を仕込んでいるのか!?)
ナックルといい、仕込み靴といい、一朝一夕で使いこなせる武器ではない。ましてや女が使うには金属の重さがネックになって使い辛い武器の筈である。
それを扱い慣れている速さと動作でもって繰り出してくる相手に、僕は僕は油断ばかりはしていられないようだと、気を取り直して応戦した。
時間にして、十数分は経っただろうか。
脳内ではその何千倍もの思考速度だった気がするが。
「よし、もういいだろう」
「はい! ありがとうございました!」
ビシッと、軍隊顔負けのきっちりした敬礼をして、シズヴィッドが直後に、派手に地面へと倒れこむ。
僕は、乱れた息を整えながら頬を伝う汗を拭う。額に張り付く髪が鬱陶しい。
(か、勝ったか……)
師匠としての面目は、一応、守れたらしい。
しかし、ここまで梃子摺るハメになるとはまったく思っていなかった。
……想定外に、かなり、……いや、ものすごく強かった。
これだけの実力があれば、仮に暴漢に襲われたとしても返り討ちにできる。
それどころか、襲ってきた暴漢を警備兵に突き出して、褒賞金でも貰って、家計の足しにでもしていそうな気がしてきた。
きっとそうだ。そうに違いない。
(この女は、心配するだけ無駄だ)
ものすごい徒労感に襲われて、僕もまた、地面の上に座りこんだ。
←back 「明日、花が咲くように」 目次へ next→
「NEWVEL」小説投票ランキング(月1回)
「HONなび」投票ランキング(日1回)
PR
最新記事
目次
アーカイブ
カテゴリー





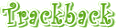
 管理画面
管理画面
